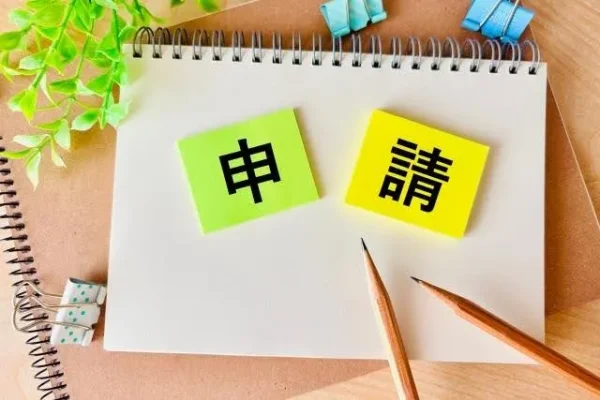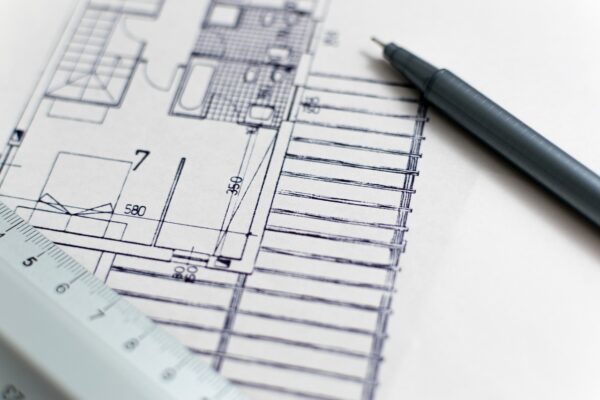「農地転用の手続きに時間が掛かり過ぎる…」
「いつ終わるかわからなくて困るなぁ…」
「書類が足りないとか言われてやり直し…一発OKなんて無理?」
農地転用の申請を行う際、このようなことで悩んでいませんか?農地転用の許可申請に係る手続きは、準備期間を含めると「半年以上」掛かることもあります。ただ、実はちょっとした工夫でこの期間を短くできることをご存知でしょうか?この記事では農地転用の手続きをスムーズに進めて、最短で終わらせるコツを紹介します。
この記事を読むことで「手続きがいつ終わるか分からない…」という不安を無くし、最短ルートで農地転用を完了することができます。「早く終わらせたい!」と思う方はぜひご参考ください。
農地転用の基本を確認する

まず初めに、農地転用に関する基本的な情報を整理しておきましょう。「農地転用とは?」「農地転用は難しい?」「農地転用許可が要らないケースもある」の3つに分けてご説明します。
農地転用とは?
田畑などの農地を農地以外の目的に利用することを「農地転用」といいます。例えば農地の用途を変更して駐車場を作る場合や、地目を変更して農地を売買する時には農地法に基づく許可(市街化区域内農地の場合には「届出」)が必要です。

出典:農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要(農林水産省)
農地転用は難しい?
農地転用の申請は「対象となる農地の区域」「広さ」「転用後の活用方法」など様々な条件によって必要な書類や手続きが変わります。もちろん個人でも対応することは可能ですが、準備する書類が多いため管理が煩雑になりがちです。申請が必要になった際は、一人で悩まずにお住まいの地域にある農業委員会へのご相談をおすすめします。
農地転用の許可がいらないケースもある
農地転用は許可制度になっていますが、例外的に許可が不要なケースがあります。主な3つの例は以下の通りです。「いくつか例外がある」ということを押さえておきましょう。
| ◯国、都道府県、指定市町村が道路などを建設するために転用する場合 ◯市街化区域内の農地を予め農業委員会に届け出て転用する場合 ◯道路、鉄道、河川など公共事業のために土地収用した農地を転用する場合 |

(出典)農地の一時利用における許可不要な場合の追加等の見直しについて(農林水産省)P.3
農地転用が完了する期間の目安はどのくらい?

対象の農地を転用する必要が出てきたら、申請に必要な準備を開始します。それでは申請前の準備から許可通知が届くまではどのくらいの期間が掛かるでしょうか。もちろん、個別の事情によって変わりますが、こちらでは標準的な期間をご紹介します。
申請までの準備期間は3カ月程度
許可申請書の作成、謄本や公図の入手、対象になる土地の測量など準備は多岐にわたります。
すべての準備が整うまでには余裕をもって「3カ月程度」を見込んでおくと安心です。相続の場合は相続手続きも必要になるため、さらに準備期間を要する想定をしておきましょう。
市街化区域の場合は1週間〜2週間程度
対象の農地が市街化区域内にある場合は、農業委員会への「届出」のみで農地転用の手続きが完了します。届出を行ってからおおよそ「1週間〜2週間程度」が目安になります。
市街化調整区域の場合は5週間〜2カ月程度
一方、市街化調整区域で農地転用を行う場合には都道府県知事の許可が必要になります。申請後、農業委員会で申請書類や現地の審査を行い、意見書を付けて知事・指定市町村長へ送付される流れになっています。申請を行ってから許可通知が届くまでにはトータルで「5週間〜2カ月程度」の期間を見込んでおきましょう。(お住まいの自治体により、許可通知までの期間は前後する可能性があります)
尚、4ヘクタールを超える農地を転用する場合には農林水産大臣との協議も必要となるため、この限りではありません。

(出典)農地の一時利用における許可不要な場合の追加等の見直しについて(農林水産省)P.2
手続きが遅れる原因は何?

ここまで申請から許可通知が届くまでの流れ、期間の目安について説明しました。次は「なぜ手続きが遅れるのか」その原因を確認していきましょう。事前に遅れる原因を把握して準備を進めることにより手続きをスムーズに完了することができます。
書類不備
申請後、申請書類に不備がある場合には農業委員会から訂正指示の連絡があります。
| ◯申請内容に不記載がある ◯申請内容に誤記載がある ◯申請書類が足りていない |
記入欄を空欄のまま提出していたり、内容に誤りがあったりする場合には、速やかに訂正し再提出を行いましょう。また、不足している書類を揃えるために時間を要する場合には、農業委員会へ相談の上、申請を取り下げ再提出をすることもあります。書類の不備は手続きに時間が掛かる主な原因になりますので、入念な準備が必要ですね。
確認漏れ
過不足なく申請書類が提出されていた場合でも、申請内容が「許可基準に達していない場合」は許可手続きが一旦保留になることがあります。
| ◯立地基準に合致していない ◯一般基準をクリアしていない |
立地基準は農地の立地や周辺環境の条件により定められており、一般基準は申請書の内容などに照らし合わせて判断されます。

家族間、近隣とのトラブル
手続きに時間が掛かる原因の一つに、家族間や近隣住民との合意形成が難しいケースがあります。生前、土地の活用方法が不確定なままで相続した土地の場合、土地活用の方向性が決まらずに時間が経過してしまうことがあります。また、周辺住民との合意形成が進まない場合には、周辺住民から役所へのクレームに発展することもあり得るため、注意が必要です。
手続きに時間が掛かることで起こる問題とは

では、農地転用の手続きに時間が掛かることにより、どのような問題が発生するのでしょうか。3つにまとめましたので、それぞれ確認していきましょう。
買い手や市場のタイミングを逃す(買い手の存在、地価の変動)
例えば、農地を宅地に変更し売却を検討していた場合、売却の時期が遅れることにより買い手との契約がまとまらない可能性が出てきます。また、土地の価格(地価)が変動する可能性もあるため、売り時のタイミングを逃すことで売却額が減少するという懸念も考えられます。
税金(固定資産税など)や維持費など金銭的な負担が増える
毎年1月1日時点での土地の所有者には、固定資産税が課されます。将来的に土地を所有する限りは税金を支払う義務が発生し、金銭的な負担が掛かります。

家族、近隣の状況も変化していく
手続きに時間が掛かることで、家族や近隣の状況も変化していきます。例えば、農地転用以外の活用方法が必要になってくるなど、土地活用の計画を見直す必要が出てくるようなケースです。
必要な事前準備を適切に行い、1回で申請を通そう

ここまで農地転用の基本、申請手続きが完了するまでの標準的な期間、手続きが遅れる原因を紹介してきました。これらの情報を踏まえた上で、1回で申請を通すために必要な準備の方法を解説します。
必要な書類をリスト化する
まず、農地転用の申請に必要な書類を確認していきます。大きく分けると「必ず準備が必要な書類」と「農地活用後の活用目的によっては準備が必要になる書類」がありますので、それぞれご紹介します。尚、お住まいの地域によって必要になる書類が異なる可能性があります。準備を始める前にお近くの農業委員会へご確認ください。
| 必ず準備が必要な書類 | 補足説明 |
| 農地の登記事項全部証明書 | ・3ヶ月以内に発行されたもの |
| 農地の所有者の住民票や戸籍の附票 | ・農地所有者の現住所がわかるもの |
| 公図の写し | ・隣接土地に関する情報(地番や地目、土地所有者、耕作者名)を記載する ・農地転用を申請する土地には色枠を付けておく |
| 位置図 | ・駅や役場、インターチェンジ、その他の公共施設からの位置がわかるもの |
| 周辺土地利用状況図 | ・住宅地図など周辺の土地利用状況が分かるもの |
| 申請地を含めた周辺の現況写真 | ・農地転用を申請する農地は赤枠で囲む ・図面には撮影した方向を記載しておく |
| 資金計画書 | ・建築費などの計画書 |
| 資力を証明できる書類 | ・預金残高証明書など |
| 活用方法によって準備が必要な書類 | 農地転用後の活用方法 |
| 相続関係を証明する書類 | ・相続により農地転用をする場合 |
| 事業計画書 農地転用後の活用を証明できる免許証の写し(宅地建物取引業免許や医師免許など) | ・事業を営む場合 |
| 建築物の平面図および立面図、建築の見積書 | ・建物を建築する場合 |
| 法人の登記事項証明書、定款 | ・法人が農地転用の申請をする場合 |
| 造成計画図 | ・開発許可を要する造成を行う場合 |
| 地積測量図 | ・一筆内の一部を農地転用する場合 |
必要な作業をリスト化する
申請書類の準備と並行して必要な作業をリスト化します。申請期限(岐阜市の場合は毎月20日)までに完了するように作業を進めていきます。必要に応じて、現地の測量の実施を行います。
| 準備作業の一例 |
| 家族間で土地の活用方法について相談、合意形成 |
| 近隣住民へのあいさつ、説明、合意形成 |
| 農業委員会への事前相談の予約 |
| 農業委員会への事前相談の実施 |
自治体によるルールの違いを把握する
申請許可の締切日は毎月10日、毎月20日など各自治体によって設定されています。申請後、農業委員会や各市町村での審査、審査会の実施日程が決まっていることがありますので、事前の確認が必要です。
役所(農業委員会含む)とのやり取りをスムーズにするコツを学ぼう

農地転用の手続きは市区町村の農業委員会が窓口になります。スムーズに手続きを進めるために押さえておくポイントを3つに分けてご紹介します。
農業委員会へ事前相談を行う
申請の準備を始める前に農業委員会へ事前相談を行いましょう。予め申請に必要な書類や手続きの締切日など注意点を確認することで、準備の抜け漏れを未然に防ぐことができます。また、来庁前に必ず予約が必要な自治体もあります。自治体のHPでご確認ください。
(参照)横浜市中央農業委員会 FAQ
窓口に進捗を確認する(いつ完了するか、期日を明確にする)
自治体によっては、問い合わせから事前相談の日時が決まるまでに1カ月以上掛かるケースもあるようです(横浜市の事例)。事前にこのような情報を知らないと、申請者が想定しているスケジュール通りに手続きが進まないことも想定されます。自治体側の処理スケジュール、手続きの進捗確認を行うようにしましょう。
事前相談を後回しにして先に土地活用の計画を進めてしまった場合「申請者が予定していたスケジュールに間に合わない!」ということもあり得ますので、十分に注意をしましょう。
(参照)横浜市中央農業委員会 FAQ
窓口に行くタイミングを工夫する
自治体により、農地転用の許可申請書の申請締切日を「毎月●●日」と定めていることがあります。例えば岐阜市の場合、市街化調整区域内の農地転用の申請は「毎月20日」が締切日に設定されています。締切日にタイミングを合わせて必要な準備を進めることで、無駄のない手続きを行うことができます。

(出典)農地を転用する場合(岐阜市)
専門家に相談して手続きを代行してもらおう

冒頭でお伝えした通り、農地転用の申請は個人での対応も可能です。しかしながら書類の準備や農業委員会と相談する時間が取れない場合は、専門家に依頼するという選択肢もあります。尚、農地転用の手続きは行政書士、土地の分筆登記、地目変更登記は土地家屋調査士が担当しています。
こちらは愛媛県行政書士会がHPに掲載している資料です。行政書士からどのようなサポートを受けられるかがイメージしやすい図になっていますのでご紹介します。

農地転用に詳しい行政書士に相談する
行政書士を探す際は「農地転用 行政書士 ○○市」と検索してみましょう。できるだけ農地転用の実績が豊富な方に依頼したいですよね。無料の相談会を実施している場合もありますので、活用をご検討ください。
面倒な書類作成、役所との交渉を代行
専門家への依頼には3万円〜10万円以上の費用が掛かる場合があります(必要なサービス内容によります)。必ず見積りを取り、慎重にご検討ください。専門家に依頼をするメリットとしては「面倒な書類作成」「役所との交渉」などに掛かる多くの手間、時間が軽減され、手続きが早く終わる点が挙げられます。
手続き後のアフターフォロー
相続を例にすると、将来的にも土地活用の問題が発生する可能性があります。何かあった際に相談ができる専門家がいることで不安を解消することにもなるのではないでしょうか。
まとめ

この記事では農地転用の基本の確認から申請後、許可通知までの期間を短くするための具体的なコツをご紹介しました。農地転用の手続きに掛かる期間は市街化区域で約1週間〜2週間、市街化調整区域では5週間〜2カ月以上かかることもあります。下記の注意点を確認し、スムーズな申請を進めていきましょう。
| ◯手続きの遅れの主な原因は「書類不備」「確認漏れ」「近隣トラブル」が多い ◯手続きの期間が長くなると買い手を逃したり、税金や維持費の負担が増えるリスクがある ◯1回で申請を通せるように事前準備をしっかり行うことが重要 ◯農業委員会とのやり取りをスムーズにするには「事前相談」「進捗確認」が効果的 ◯近隣トラブルを防ぐために、事前にあいさつや説明を行う ◯専門家に依頼することで迅速に手続きを進められる可能性が高い「農地転用を早く終わらせたい」場合には利用を検討してみましょう |